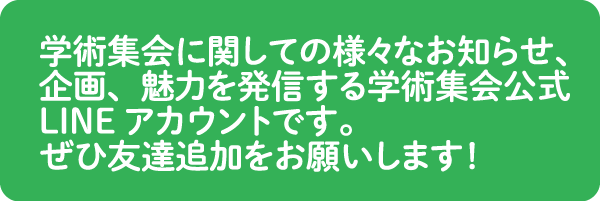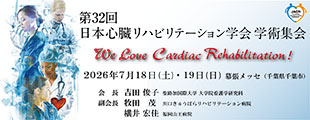演題募集・登録
募集期間
2026年2月17日(火)12:00 ~ 4月8日(水)23:59
- 演題募集期間内であれば、マイページにて応募した演題を何度でも修正いただけます。
- セキュリティー上パスワードに関してのお問い合わせには応じられません。初回ログイン済で、お忘れの場合は「※ID・パスワードを忘れた方」より再発行してください。
- 締切当日はアクセスが集中し、演題登録に支障をきたすことが考えられますので、余裕をもってご応募ください。
- 募集期間の延長を実施しない場合もございますので上記登録期間中に必ずご応募をお済ませください。
- 締切後の修正はお受けできませんのでご注意ください。
募集演題
企画セッション演題
応募時、企画セッションに不採用の場合に一般演題での発表を希望するか、取下げを希望するか、いずれかをご指定ください。
若手シンポジウム
以下のシンポジウムは座長・演者ともに主には40歳代以下で構成する予定ですので、40歳代以下の皆様からのご応募を優先して採択したいと考えております(もちろんそれ以外の方々も応募いただけます)。
「U40世代と語る 心筋症診療の "リアル" ~遺伝子解析から最新治療まで、明日の診療につながる知識を共有する~」
- 企画趣旨
- 心筋症診療は近年、画像診断や遺伝学的検査の進歩、さらには新規治療薬の登場により大きく変貌を遂げている。本セッションでは、診断・リスク層別化から治療選択までのプロセスを整理しながら、現場で活躍するU40世代の医師たちが症例をベースに議論する。診療のリアルを通して「個々の症例にどう立ち向かうか」を共有し、明日の診療のレベルアップにつながる場を提供する。
「心不全治療における画像診断の実践と可能性:若手医師・技師が拓く多職種アプローチ」
- 企画趣旨
- 心不全診療における画像診断は、病態把握から治療評価・予後予測に至るまで極めて重要な役割を担っている。本セッションでは、Under40の若手医師および放射線技師が、各施設での実践的な画像活用法を紹介。CT、MRI、核医学など多様なモダリティの強みを活かした取り組みを通じて、心不全診療における画像診断の未来について多角的に議論する。
「その判断、本当に正しかった? ― 現場で迷った循環器集中治療症例を振り返る」
- 企画趣旨
- 循環器集中治療の現場では、ガイドラインだけでは解決できない「正解のない状況」に直面することが少なくありません。本セッションでは、若手の医師・看護師・リハビリ職・臨床工学技士・栄養士など多職種から、判断に迷った症例を広く募集します。合わせて各施設で活用されているプロトコールや判断の経過を共有いただき、症例をもとに治療方針、ケア、家族対応まで含めて議論します。明日からの診療に役立つ視点や工夫を探り、循環器集中治療の質の向上を目指します。
「広がるデバイスナースの活動~患者さんを支える植込み型心臓不整脈デバイス認定士~」
- 企画趣旨
- 植込み型心臓不整脈デバイス認定士資格を取得した看護師は増加傾向にあるが、資格取得後「資格を活かした活動方法がわからない」「実際の活動内容を聞いてみたい」という方は多いのではないか。看護師介入による診療報酬加算はなく、様々なジレンマもあると考える。このセッションでは植込み型心臓不整脈デバイス認定士である看護師に、実際の活動や患者介入を紹介いただき、聴講者の今後の活動のヒントとなることを期待している。
「弁膜症に対するマルチモダリティ評価 ~Beyond guidelines~」
- 企画趣旨
- 弁膜症診療において、成因および重症度評価の中心に心エコーがあることは疑いの余地がないが、近年の画像技術の進歩に伴い、CTやMRIを弁膜症評価に活用できるようになってきた。ガイドラインに記載されているような大動脈弁の石灰化の評価だけでなく、心電図同期造影CTによる僧帽弁尖及び弁下組織の評価や、低腎機能症例における心電図同期単純CT/MRIの組み合わせによる大動脈基部構造の評価など、特にカテーテル治療の進歩に伴い様々な工夫をこらす施設も見られる。本セッションでは、弁膜症に対するマルチモダリティ評価の最前線について、心エコーを基盤としつつ、CT・MRI所見を統合した包括的評価の実際を紹介頂き、議論したい。
「そのAF、どう考える?―若手が悩む心房細動治療のグレーゾーン」
- 企画趣旨
- 心房細動治療の適応に悩む症例は、若手医師が日常臨床で直面する課題である。本セッションは、こうしたガイドラインだけでは判断が難しい「グレーゾーン」に焦点を当てる。治療法の選択やフォローアップ方針において、全国の若手医師から寄せられる「悩み」を座長、演者、フロアが一体となって議論し、より良い治療方針の形成を目指す。
「この患者にどう介入する?―実臨床の葛藤から学ぶSHDケースカンファ―」
- 企画趣旨
- 介入か、経過観察か、カテーテルインターベンションか、外科介入か。インターベンションの方法が多様化し、現場での治療方針決定に悩むことが増えている。現場で治療方針の選択に悩んだ構造的心疾患症例を募集する。本セッションは若手セッションとして実施する。若手医師でハートチームの議論軸、画像・解剖の要点、患者背景を踏まえた最適解を検討する。
「ハートでつなぐ、動き出す未来―多職種連携における薬剤師の役割―」
- 企画趣旨
- 心不全、糖尿病、慢性腎臓病、がん治療など多様な疾患が心臓に与える影響が注目される中、薬剤師は“心臓を守る”視点を地域における医薬連携において強く求められている。本シンポジウムでは、心・腎・代謝(CKM)連関に基づく病態を踏まえ、薬物療法の最適化やモニタリング、医師とのタスクシェアを通じて心臓を守る薬剤師の新たな役割を探る。
「循環器診療の最前線―循環器救急に潜む罠―」
- 企画趣旨
- 循環器内科医の主戦場の一つが救急外来であり、時間的猶予のない状況下で数多くの判断を迫られる。日常診療の中で誰もが一度はヒヤリとする、あるいは苦い経験をした症例に遭遇することは少なくない。本セッションでは、全国からそのような実体験に根差した症例を募集し、循環器救急におけるpitfall(診断・治療上の落とし穴)について討議を行う。特に若手から中堅医師の明日に役立つ、適切な診断・治療方針を選択するための思考過程や判断のポイントを共有することを目的とする。
シンポジウム
以下のシンポジウムは、世代を問わず幅広い先生方からのご応募を歓迎いたします。
「日本人ACSの抗血栓治療を日本発の最新エビデンスから考える」
- 企画趣旨
- 日本人における急性冠症候群(ACS)の抗血栓療法は、出血リスクと虚血予防のバランスという難題を常に抱えている。近年の新規抗血栓薬や短期DAPT戦略など、エビデンスの蓄積とともに日本人特有のリスクプロファイルに基づく最適化が求められている。本シンポジウムでは、国内外の最新研究をふまえ、特に2026年欧州心臓病学会で発表予定の近畿大学 中澤学教授による日本多施設前向き研究の成果を基盤に、日本人ACSにおける抗血栓治療の未来像を多角的に議論する。
「主要ガイドラインに見る弁膜症早期治療のコンセンサスと将来像」
- 企画趣旨
- 弁膜症診療では、古典的には重症化に伴う症状の出現を治療開始の基準としてきた。しかし、低侵襲治療の進歩により、臨床現場では早期発見・早期治療へと舵を切りつつある。近年、多くの研究が早期治療の利点と限界を示しているものの、世界各国の主要ガイドラインでは早期介入の閾値や推奨度に相違が見られるのが現状である。本セッションでは、各国ガイドラインにおける早期治療の位置づけを比較し、どの点がコンセンサスとして確立され、どの点がなお議論の余地を残しているのかを明らかにする。さらに、現存するエビデンスギャップを整理しながら、弁膜症治療の将来像を展望する。
「The息切れ外来 ~当院の息切れ外来紹介します~」
- 企画趣旨
- 近年、心不全の初期症状である「息切れ」に着目し、早期診断と介入を目指す専門外来「息切れ外来」が注目されている。本セッションでは、息切れ外来の開設、診療体制、運用の工夫や課題を紹介する。息切れを主訴とする患者にどう対応すべきかを具体的に示すことで、心不全診療の最前線を共有するとともに、かかりつけ医や若手医師の診療にも役立つ知見を提供する。
「ISCHEMIA試験後の慢性冠症候群診療:イメージングが拓くRisk based approach」
- 企画趣旨
- 近年、ISCHEMIA試験を契機として、虚血評価が本当に慢性冠症候群(CCS)の予後を予測し得るのか、あるいは新たな評価指標が求められているのか、議論が続いている。本セッションでは、CT、MRI、核医学、冠動脈生理、血管内イメージングの各分野のエキスパートが、それぞれのモダリティの可能性と限界を臨床的視点から解説する。CCSのリスク層別化における戦略的活用について多角的に議論し、画像診断の統合的な活用を再考する機会とする。
「心電図の深淵を覗く:波形を「見る」から病態を「観察する」へ」
- 企画趣旨
- 日常診療で最も頻用される心電図。近年では心電図検定などを通じて、その面白さに広く触れることができるようになり、循環器医師に限らず学ぶ医療者が増えている。しかし、その勉強方法を詰め込みに頼っていないだろうか?情報の深さと広さを、我々は本当に理解しきれているだろうか?
- 本セッションでは、誰もが見ている「心電図」を観察し続けてきた研究者から、12誘導心電図のポテンシャルに関する演題発表を行う。
- 心電図検定に臨む若手医師やコメディカルにとっても、単なるパターン認識ではない「考える読影」の面白さと、将来の展望を提供することを目的とする。
「それ、本当に日本でも通用する?~海外心リハ研究 vs 日本のリアル~」
- 企画趣旨
- 心臓リハビリテーションに関する臨床研究が実施され、そのエビデンス構築が進展している。しかしながら、多くの研究が海外を舞台に行われており、日本の医療制度や患者背景を踏まえると研究成果をそのまま臨床へ適応できるのかは悩ましい。本セッションでは、最近発表された心臓リハビリテーション関連の注目研究を題材に、日本の現場での実装可能性や課題を検討し、「本当に通用するのか?」を問い直す。
「心不全薬物療法における薬剤師のハンド ~カードはメドレク&ケアイコウ~」
- 企画趣旨
- 心不全薬物療法では、再入院予防と予後改善のため、入院から退院後まで切れ目のない支援が不可欠である。
本シンポジウムでは、心不全入院患者に対するケア移行とMedication Reconciliation(メドレク)に焦点を当て、同一医療機関内であっても急性期病棟(ICU等)と一般病棟という異なるフェーズで薬剤師が担う役割と直面する課題を共有する。さらに、連携を強化するための実践的方策を議論し、心不全患者のアウトカム改善に向けて薬剤師が取り組むべき課題を明確化する。
「より多くの視点で看護する~新たな心不全チームアプローチ~」
- 企画趣旨
- 心不全診療のチーム医療は年々進化し、看護師の役割も多岐にわたっている。専門・認定看護師、心不全療養指導士、心臓リハビリテーション指導士、診療看護師などが多角的な視点で強みを活かした実践や連携を進めている。2024年診療報酬改定で在宅療養指導料に慢性心不全患者が追加され、療養支援強化の方針が示された。各看護師の立場から診療報酬加算を視野に入れた活動や多職種協働について発表を行い、新たなチーム医療の形を考える場としたい。
「みんなで繋ぐ心不全ケアのバトン~多職種連携から共創へ~」
- 企画趣旨
- 本セッションは、従来の心不全ケアにおける連携を再考し、その現状と課題を明らかにするとともに、真の意味での「連携」とは何かを議論するものである。施設間・施設-地域・地域間における多様な実践事例を通じて、形式的な枠組みにとどまらず、多職種が専門性を補完し合い、学び合うなかで、新たなケアの形を「共創」する姿勢を提示する。
各地域の特色を生かした実践的取り組みを紹介し、心不全ケアの質的向上に向けた具体的方策を共有し、次の一歩につなげることを目的とする。
一般演題・ポスターセッション
応募カテゴリー
A.虚血性心疾患
| 小項目 | |
|---|---|
| A-1 | 急性冠症候群 |
| A-2 | 狭心症 |
| A-3 | その他の虚血性心疾患 |
| A-4 | 冠循環・心筋虚血 |
| A-5 | 冠動脈インターベンション |
B.心不全
| 小項目 | |
|---|---|
| B-1 | 心不全:病態 |
| B-2 | 心不全:薬物治療 |
| B-3 | 心不全:非薬物治療 |
| B-4 | 心肥大・心機能・神経体液性因子 |
C.心筋・弁膜疾患
| 小項目 | |
|---|---|
| C-1 | 心筋症 |
| C-2 | 心筋炎 |
| C-3 | 二次性心筋症・アミロイドーシス・サルコイドーシス等 |
| C-4 | 弁膜症 |
| C-5 | カテーテルインターベンション(大動脈弁) |
| C-6 | カテーテルインターベンション(僧帽弁 他) |
D.心膜疾患・心内膜炎
| 小項目 | |
|---|---|
| D-1 | 心膜疾患 |
| D-2 | 感染性心内膜炎 |
E.不整脈・心電図
| 小項目 | |
|---|---|
| E-1 | 上室性不整脈(心房細動・粗動を含む) |
| E-2 | 心室性不整脈 |
| E-3 | カテーテルアブレーション |
| E-4 | 植え込み型デバイス(ペースメーカ、ICD等を含む) |
| E-5 | 心電図・体表面電位図・ホルター心電図 |
F.血管疾患
| 小項目 | |
|---|---|
| F-1 | 大血管疾患 |
| F-2 | 末梢動脈疾患 |
| F-3 | 脳血管疾患 |
| F-4 | 静脈・リンパ疾患 |
| F-5 | 血管・内皮機能 |
| F-6 | 血管インターベンション:頸動脈・大動脈・腎動脈・末梢血管ほか |
G.肺血管疾患・肺循環
| 小項目 | |
|---|---|
| G-1 | 肺高血圧 |
| G-2 | 肺血栓塞栓症 |
| G-3 | 肺循環 |
H.小児・先天性心疾患
| 小項目 | |
|---|---|
| H-1 | 小児先天性心疾患 |
| H-2 | 小児後天性心疾患 |
| H-3 | 成人先天性心疾患 |
| H-4 | カテーテルインターベンション |
I.高齢者・性差・腫瘍
| 小項目 | |
|---|---|
| I-1 | 高齢者疾患 |
| I-2 | 性差医学 |
| I-3 | 腫瘍関連疾患 |
J.救急・突然死・自律神経・ストレス・心身
| 小項目 | |
|---|---|
| J-1 | 循環器救急・突然死・ショック・心肺蘇生 |
| J-2 | 自律神経・ストレス・心身医学 |
K.疫学・予防・医療経済
| 小項目 | |
|---|---|
| K-1 | 疫学・予防 |
| K-2 | 医療経済 |
L.心血管危険因子
| 小項目 | |
|---|---|
| L-1 | 脂質異常症 |
| L-2 | 糖尿病 |
| L-3 | 高血圧 |
| L-4 | 肥満・メタボリック症候群 |
| L-5 | 睡眠呼吸障害(呼吸器疾患を含む) |
| L-6 | がん治療関連心血管障害 |
| L-7 | その他の危険因子(喫煙・歯周病を含む) |
M.心血管エコー
| 小項目 | |
|---|---|
| M-1 | 心エコー(経食道エコーを含む) |
| M-2 | 血管エコー(体表) |
| M-3 | 負荷エコー |
N.心血管イメージング(非観血的)
| 小項目 | |
|---|---|
| N-1 | 冠動脈CT |
| N-2 | CT・MRI(その他) |
| N-3 | 心臓核医学(SPECT,PET) |
O.心血管イメージング(観血的)
| 小項目 | |
|---|---|
| O-1 | 血管・心腔内エコー・OCT・血管内視鏡 |
| O-2 | プレッシャーワイヤー(FFR)・ドプラフローワイヤー |
P.運動負荷・心臓リハビリ
| 小項目 | |
|---|---|
| P-1 | 運動負荷・薬物負荷試験 |
| P-2 | 心疾患リハビリテーション |
Q.外科治療
| 小項目 | |
|---|---|
| Q-1 | 外科治療:虚血性心疾患 |
| Q-2 | 外科治療:弁膜症 |
| Q-3 | 外科治療:血管疾患 |
| Q-4 | 外科治療:不整脈 |
| Q-5 | 外科治療:心不全(左室形成・補助人工心臓・心臓移植) |
| Q-6 | 外科治療:小児・先天性疾患 |
R.腎
| 小項目 | |
|---|---|
| R-1 | 腎疾患・慢性腎臓病 |
S.再生医学
| 小項目 | |
|---|---|
| S-1 | 心臓 |
| S-2 | 末梢血管 |
| S-3 | 組織工学 |
T.メディカルスタッフ
| 小項目 | |
|---|---|
| T-1 | 看護・クリニカルパス・介護 |
| T-2 | 臨床検査 |
| T-3 | 医用工学 |
| T-4 | リハビリテーション |
| T-5 | 放射線 |
| T-6 | 薬剤 |
| T-7 | 栄養ほか |
U.ハートチーム
| 小項目 | |
|---|---|
| U-1 | ハートチームによる医療 |
V.医療連携
| 小項目 | |
|---|---|
| V-1 | 地域医療 |
| V-2 | 実地医家 |
W.その他
| 小項目 | |
|---|---|
| W-1 | AI |
| W-2 | 新型コロナウィルス関連 |
| W-3 | その他 |
X.症例報告
| 小項目 | |
|---|---|
| X-1 | 虚血性心疾患 |
| X-2 | 心不全 |
| X-3 | 心筋症・心筋炎 |
| X-4 | 弁膜症・感染性心内膜炎 |
| X-5 | 不整脈 |
| X-6 | 大血管疾患 |
| X-7 | 肺高血圧・肺血管疾患 |
| X-8 | 先天性心疾患 |
| X-9 | 腫瘍循環器関連疾患 |
| X-10 | その他 |
メディカルスタッフYIA
メディカルスタッフの皆様よりYoung Investigator's Award(YIA)のご応募を受付ます。
応募条件:2026年9月13日時点で40歳未満の医師以外のメディカルスタッフが筆頭著者である事。その他の応募条件は一般演題と同様です。
- 応募の際、不採用の場合に一般演題での発表を希望するかどうか、ご指定ください。
J-NECST(日本心臓病学会 若手の会)企画Award
Case Presentation Award
これは、臨床研究法の影響などで若手が研究を行うハードルが上がっている中で、心臓病学会として重視している「症例を大切にする」との観点で、症例報告で競争する場を設けたいという趣旨から企画した。Winnerには賞品を進呈する。
卒後10年以内(2017年卒業まで)の先生を対象とし、予選1、 予選2のプレゼンテーションで選ばれた上位数名(2025年度は3名)が決勝に進む。
※応募の際、不採用の場合に一般演題での発表を希望するかどうか、ご指定ください。
Retrospective Research Award
若手医師(卒後10年以内)を対象に、規模や準備のハードルが比較的低い後ろ向き研究を発表する機会を提供することで、研究者としての第一歩を後押しすることを目的としている。 “臨床現場での疑問”や“着想”段階のアイデアに対しても、建設的なフィードバックやさらなるブラッシュアップにつながるアドバイスを得られる機会を設けることで、将来的な論文化や多施設研究への道筋を描くきっかけとし、次世代の臨床研究を牽引する人材の発掘・育成を目指す。
応募資格:卒後10年以内(2017年卒業まで)
応募対象等詳細は以下をご確認ください。
ここをクリック
-
応募対象(研究種別・データソース):
1) 対象となる研究
本Awardの対象は、既存データを用いた後ろ向き解析(retrospective analysis)とする。ここでいう既存データとは、応募時点で収集が完了しているデータ(診療録、レジストリ、既存コホート等)を指し、本Award応募のために新たな前向きデータ収集を開始しないことを要件とする。具体的に「応募可」とする例- 診療録・検査データ・画像データを用いた後ろ向き観察研究(単施設/多施設いずれも可)
- 疾患レジストリ(前向きに収集されていても可)を用いたpost-hoc解析/二次解析
- 前向き観察コホートで収集済みデータを用いた事後解析
- 既存データを用いた予後解析、リスクモデル、サブグループ解析、機械学習解析等(データが臨床由来で、解析が後ろ向きであること)
2) 対象外とする研究
以下は本Awardの趣旨(若手が実施しやすい後ろ向き研究の奨励)から外れるため、対象外とする。A. 新規の前向きデータ収集を要するもの- 本Award応募のために新たに前向き登録・追跡・検査・アンケート等を開始する研究
- 介入の有無にかかわらず、prospective studyとして新規に設計・実施中の研究
B. 介入研究(RCT等)由来のデータを用いる解析- 前向きRCT(無作為化比較試験)データセットを用いたpost-hoc解析/サブ解析/二次解析(サブグループ解析を含む)は対象外
C. 研究形式が本Awardの趣旨と異なるもの- システマティックレビュー/メタ解析
- 基礎研究、動物実験、in vitro研究
- 学会・行政・企業等により整備された全国規模データベース(例:全国レジストリ、レセプト等)を用いた研究については、既存変数の二次利用のみで完結する解析は原則対象外とする。ただし、当該データに加えて応募者が主体となり追加のカルテ抽出による新規変数作成、アウトカム判定、品質管理等のデータ生成に実質的に関与している場合は、趣旨に照らして受理することがある(J-NECST判断)。
※応募の際、不採用の場合に一般演題での発表を希望するかどうか、ご指定ください。
日本サイコカーディオロジー学会-日本心臓病学会ジョイントシンポジウム
「身近な依存症と心血管疾患:循環器心身医学から考える生活習慣改善の最前線」
- 企画趣旨
- 心血管疾患の予防や治療において、飲酒、喫煙、過食、運動不足などの生活習慣をどのように改善するかは、日常診療の重要な課題である。これらの行動には依存的要素を含む場合もあり、患者が望んでいても自発的な改善が難しいことが少なくない。本シンポジウムでは、循環器内科と精神科がタッグを組み、生活習慣と依存症のメカニズムを整理し、アルコール、喫煙、肥満、高血圧などの主要リスクを対象に、依存症治療や認知行動療法に基づく行動変容支援の要点臨床で想定される課題、患者支援における心理学的視点の有用性について議論する。
応募資格
心臓血管病学研究の推進とその成果に関する内容について、どなたでも応募いただけます。ただし、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針を遵守して医学系研究を実施していること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/kenkyujigyou/i-kenkyu/index.html
応募方法
演題のご応募は、第74回日本心臓病学会学術集会専用システムよりご登録をお願いいたします。
メール等での受付はできません。
今回のシステムは演題登録・参加登録一括管理システムとなりますのでまずは、マイページのご作成をお願いいたします。
本ページ下部の「マイページ作成・ログインページ」ボタンよりご登録ください。
※推奨環境
ブラウザはMicrosoft Edge、Chrome、Safariです。各ブラウザの最新バージョンを利用してください。
PC・スマートフォンいずれからのご登録も可能です。
2026年1月27日までに日本心臓病学会へ入会済みの方
「日本心臓病学会会員の方はこちら」より新規登録をお願いいたします。
2026年1月27日以降に入会された方、入会手続き中の方、非会員の方
「基準日以降に入会した会員/非会員の方はこちら」より新規登録をお願いいたします。
会員番号の入力について
マイページ作成にあたっては、会員・非会員を問わず、会員番号欄への入力が必須です。
- 本学会会員の場合:正確な会員番号(7桁)を入力してください。
会員番号を入力後、「会員情報連携」ボタンをクリックすると、2026年1月27日時点の会員データが反映されます。会員データに修正が必要な場合は、手入力で修正してください。 - 2026年1月27日以降に入会された方、または入会手続き中の場合:会員番号には 9999999(7桁) を仮入力し、すべて手入力で登録してください。
- 非会員の場合:会員番号に 0000000(7桁)を入力してください。
会員番号の確認
ご自身の会員番号が分からない場合は日本心臓病学会ホームページ内[会員番号について]をご参照ください。
共同演者の会員番号は、[会員のページ]内の[会員名簿の検索]メニューよりご確認いただけます。
※会員への留意事項
演題応募システムで入力・修正された内容は、学会の会員情報には反映されません。
会員情報の変更・修正をご希望の場合は、日本心臓病学会ホームページ内[会員のページ]より、ご自身でお手続きください。
入会のお手続き
入会をご希望の方は、「入会について/オンライン入会申込み」よりご入会の手続きをお願いいたします。
学会入会に関するお問い合わせ先:
一社)日本心臓病学会事務局
E-mail:admin@jcc.gr.jp
応募セッション・企画の選択
- ①企画セッション演題「若手シンポジウム」・「シンポジウム」:ご希望のセッションをご選択ください。
- ②一般演題・ポスターセッション:ご希望の「応募カテゴリー」を選択してください。
- ③メディカルスタッフYIA
- ④J-NECST公募セッション:Case Presentation Award、Retrospective Research Awardよりご選択ください。
- ⑤日本サイコカーディオロジー学会-日本心臓病学会ジョイントシンポジウム
- ②を除いて、応募の際不採用の場合に一般演題での発表を希望するかどうか、ご指定ください。
応募要項
発表者、共同演者の登録
- 発表者は、必ず筆頭演者として登録してください。
- 共同演者:最⼤15名(筆頭演者を含まない)
- 所属機関:最⼤15施設
- 著者に複数所属を指定することができます。
共同演者は、会員・非会員を問わず、会員番号欄への入力が必須です。
先述の【会員番号の入力について】をご参照ください。
抄録言語:日本語
抄録文字数:全角文字1字、半角英数字0.5字として換算
- 演題名 :全角60文字以内
- 抄録本文:(図表のない場合)800文字以内、(図表のある場合)530文字以内
図表(任意):一点のみ、データ容量は1MB以内とする。
入力時の注意事項
- 上記の字数を超えると登録できません。
Microsoft Wordファイルでカウントした文字数と演題登録システムに表示される文字数が異なる場合もあります。システムに表示される文字数をご確認ください。 - 全角⽂字は1⽂字として、半角⽂字は0.5⽂字として数えます。
- アルファベットの直接⼊⼒は半角英数ですので0.5⽂字となります。
- 英字および数字は、スペースを含め、半角で入力してください。
- <SUP>などのタグは⽂字数には換算しません。
- 半角カタカナや丸数字・ローマ数字・特殊⽂字等の機種依存⽂字は使⽤できません。
- Microsoft Wordファイルで装飾した文字をそのままコピー&ペーストされると装飾〈太字、イタリック、アンダーライン、上付き文字(例:Na+)や下付き文字(例:H2O)〉 が自動的に外れます。装飾〈太字、イタリック、アンダーライン、上付き文字(例:Na+)や下付き文字(例:H2O)〉については、コピー&ペーストした後、抄録入力欄上部の編集パレットボタンをご使用の上、編集ください。
- 文字化けが発生し保存や投稿ができない場合は、運営事務局(jcc2026@zenith-j.co.jp)へメールにてご連絡ください。
登録演題の投稿・修正・取下げについて
1. 入力内容の投稿について
投稿時は、「投稿」ボタンをクリックし、次画面で入力内容をご確認のうえ、必ず「投稿確定」をクリックしてください。これで、演題が「投稿」されます。
- 一時保存されたい場合は「保存」ボタンをクリックしてください。保存時は「未投稿」ですので完成されましたら必ず「投稿」してください。
- ステータスが「未投稿」のままですと運営事務局で登録内容の確認ができませんのでご注意ください。
- 演題登録の入力内容がそのままプログラムや抄録集に掲載されます。原則として校正されませんので、タイプミスには充分ご注意ください。
2. 演題登録後完了後、演題登録システムより受領通知が自動的に電子メールにて配信されますので、ご登録されたE-mailアドレスを必ずご確認ください。1日以上経過しても受領通知メールが届かない場合は、マイページ「登録演題一覧」より登録演題のステータスが「投稿済み」となっているかや迷惑メールフォルダをご確認ください。
以上をご確認いただいたうえで、受領通知メールが届かない場合は、運営事務局(jcc2026@zenith-j.co.jp)までご連絡ください。
- ステータスが「未投稿」のままですと運営事務局では確認ができません。
3. 演題登録期間中は、投稿済みであっても何度でも修正が可能です。マイページへログインのうえ「登録演題一覧」よりご希望の演題を選択ください。
4. 投稿済みの演題を取り下げる場合は、ご自身で削除できませんので運営事務局(jcc2026@zenith-j.co.jp)までご連絡をお願いいたします。
演題の受領通知および採否通知
演題応募時にご入力いただいたE-mailアドレス宛てに受領通知が送信されます。
応募演題の採否は、査読委員の評価に基づき、最終的に会長が決定いたします。
発表日時の指定はできませんので予めご了承ください。
採否通知は、受領通知を送信した同じE-mailアドレス宛てに、下記日程での通知を予定しています。
採否通知送付予定日 :2026年6月頃
臨床研究の利益相反(Conflict of Interest, COI)と研究倫理について
COI申告
筆頭発表者は、筆頭演者および共同演者すべてを取りまとめてCOI自己申告および開示を行うことが必要です。演題登録時、演題の内容に関連した企業との利益相反状態の有無を申告してください。
必ず「利益相反(COI)マネジメントに関するガイドラインおよび細則」をご確認の上、演題登録時から遡って過去3年間のCOI状態を演題応募画面のCOIに関する項目に回答してください。また、筆頭演者は、共同演者も含めた全員のCOI状態を発表スライド上に開示してください。
倫理面への配慮
「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」に則り、発表内容が倫理的問題に配慮されていることをご確認のうえ、演題応募時に申告してください。
注意事項
- 応募されたすべての演題の著作権は日本心臓病学会に帰属します。
- 国内の他学会または学会誌にてすでに発表された演題と同一の演題は応募できません。
- 応募締切後の変更及び共著者の追加、変更はお受けできません。十分ご注意ください。
- 演題登録に関する問い合わせは、第74回日本心臓病学会学術集会 運営事務局
jcc2026@zenith-j.co.jpまでご連絡ください。
個⼈情報保護について
本学会の演題登録システムは株式会社翔薬の演題登録システム(Gsystem)に委託しております。
参加登録、演題登録にて収集いたしました⽒名、連絡先、E-mailアドレスは事務局からのお問合せや発表通知に利⽤いたします。また、⽒名や所属、演題名、抄録本⽂は、ホームページ及び抄録集に掲載いたします。いただいた個人情報は本目的以外に使⽤することはございません。⼀切の情報が外部に漏れないように管理を徹底いたします。
演題登録
下記ボタンを押下ください。
演題登録に関するお問合せ
第74回日本心臓病学会学術集会 運営事務局
- 株式会社ジーニスコンベンションサービス
- E-mail:jcc2026@zenith-j.co.jp
- ※原則メールにてお問い合わせくださいますようご協力をお願いいたします。